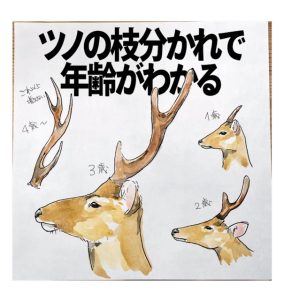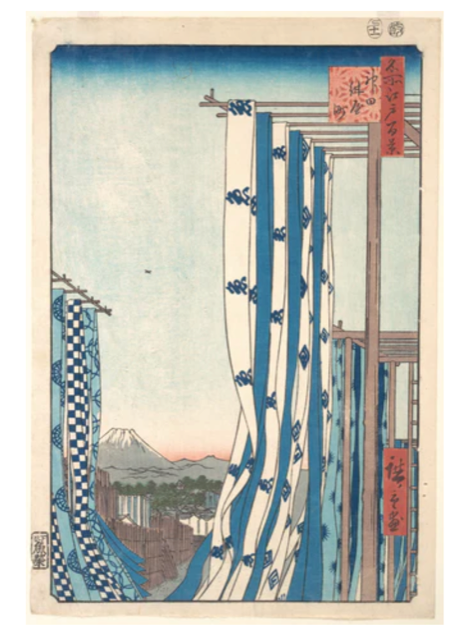秋と言えば、『食欲の秋』!
美味しいものを食べるために使う道具である歯。
今日は、一番悩んでいる方が多い義歯(入れ歯)にスポットライトを当て説明したいと思います。入れ歯と言っても種類は様々です。
まず大きく分けると、保険診療と自由(自費)診療があります。
保険の入れ歯『樹脂床』
当院の信頼する技工士が作成し、調整するので問題はありません。しかし、保険の縛りがあるため使う材料などの自由の幅がありません。
自由診療(自費)診療のものは、材料や手間がかかるためより精密に仕上がります。いろいろな材料の義歯があるので患者さんの希望はもちろんですが、口腔内の状況により適しているものを判断し提案することができます。
以下が自由診療の義歯になります。

『金属床』チタン床・金床・コバルトクロム床などから選択します。
金属床は、薄く仕上げれるため違和感や話にくさを軽減します。熱伝導性も良く、ぴったりとした装着感があります。部分的な入れ歯も可能です。
『コンフォートデンチャー』

入れ歯の裏面に生体用シリコーンというクッションで覆います。この弾力のおかげで咬んだ時の歯茎への負担を軽減、また吸着力にも優れていると言われています。
『ブレードティースデンチャー』

この入れ歯は、人工歯に特徴があります。咬砕力を増すことで顎堤の圧を軽減し、この金属部に力が集中することで小さ力で効率よく食べ物を咬み切ることができます。上の入れ歯の歯に金属がつくため見た目ではわかりません。
『ノンクラスプデンチャー』

通常保険だと金属になってしまう留め金が透明なもので、さらに目立ちにくくなりました。
『イボカップデンチャー』
ヨーロッパのリヒテンシュタインで開発された大変精度の優れた義歯製作システムによってつくられた入れ歯です。見た目は、保険のと変わらないと思う方もいるようですが並べると審美性は高く精密なためつけ心地は全く違います。
他『テレスコープ義歯』『アタッチメント磁性義歯』なども治療可能です。
当院の治療手順は、基本的に今お使いの入れ歯を修正し痛みを取り
それから希望の方には新しい義歯を作製します。咬めない状態がないよう治療を進めます。
入れ歯でお困りの方は、ぜひ当院の治療を受けていただきたいと思います。
開業47年、知識と経験から最善の治療を提供したいと思います。