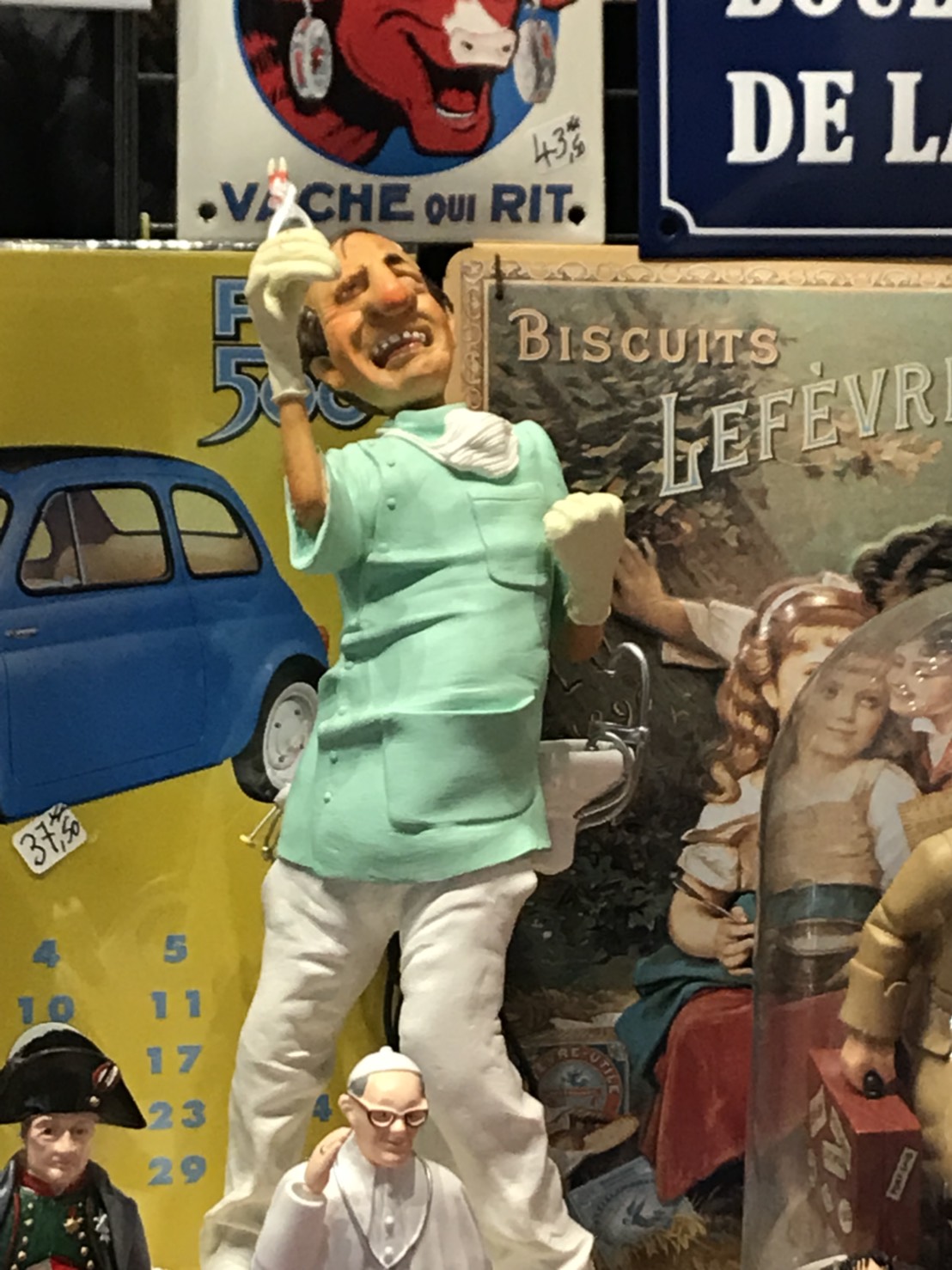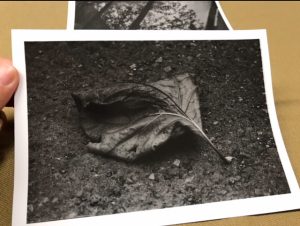以前も紹介した『人間はなぜ歯を磨くか』石川純先生の本から、今日は『歯ブラシとは何か』についてお話したいと思います。
少し面白い研究結果がこの本には載っています。それは、野生ザルと飼育ザルの口の中を比べると、野生のサルの口の中は清潔そのもので、虫歯も歯周病も認められませんでした。アザラシやカリブー(トナカイ)の生肉ばかり食べていたエスキモーは、虫歯が全くありませんでしたが文明人と接触するようになったとたんに虫歯になったとわかっています。この結果をみてみると、虫歯や歯周病は文明の進化で見られるようになった文明病なのかもしれません。
もしそうだとしたら、私たちが日に三度欠かさずに食べている食べ物がなぜ顎を衰えさせ、歯をダメにしてしまうのでしょう。
現代人の食べ物は、甘く、柔らかく、温かいことが大きな特徴と言えます。私たちが米や麦をご飯やパンに加工して食べることは、炭水化物の消化吸収の効率を著しく高める点からみれば、きわめて賢明な方法に違いありません。しかし、ご飯やパンをはじめとして、加工されたほとんど全ての食べ物は自然のままの食べ物に比べて問題をかかえています。それは、軟らかく、口に残りやすく、歯の表面に付着停滞し微生物の温床になるという点です。このような食べ物は、例え歯並びが良い場合でも歯の間や咬む面の溝に残りやすい危険をはらんでいます。傾斜していたり、捻転している歯の周囲、あるいは歯並びが良くない部分などさらには人工歯の周りにはかならずといっていいほど残ります。
もし野生のサルや加工食品のない時代の原始人と同じように、繊維にとんだ硬い食べ物をよく噛んでいれば仮に汚れがたまりやすいところがあったとしても、強い咀嚼によってそれは吹き飛ばされてしまいます。私たちが毎日何の疑いももたずに食べ続けてきたもの、それはすべて文明の所産であり、人工の手を加えたものばかりです。
『歯ブラシとは、何か?』
それは、繊維性の硬い自然の食べ物を忘れ去った、現代人の汚れた口をもう一度清潔にするための代用繊維といえるのではないでしょうか。

以前の記事 ➡ 人間はなぜ歯を磨くか